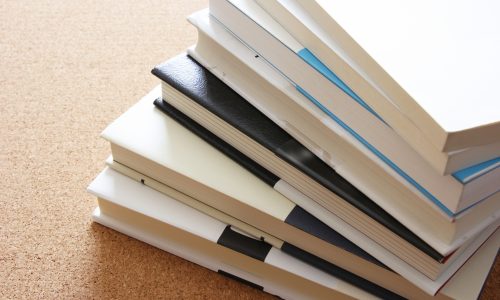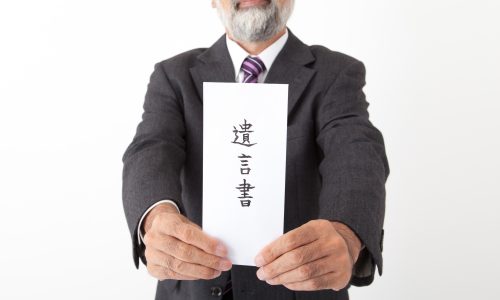「亡くなった親が実は連帯保証人になっていた」親が亡くなってからこの事実に気づいて慌てるという方は珍しくありません。
今回の記事では、連帯保証の重い責任について紹介し、そのうえでどうすれば相続人が借金の返済義務から免れられるかを説明します。
加えて、よくある連帯保証人が関連する遺産相続トラブルも紹介しているので、最後までお読みください。
目次
被相続人が連帯保証人の場合は、連帯保証も相続する
親など被相続人が他人の連帯保証人となっていた場合、相続人が財産を相続するならば、その連帯保証の立場も相続することになります。
相続するということは、マイナスの財産(借金や未払いの費用、債務保証など)を含めた全ての財産を承継することになるからです。
そもそも連帯保証とは?

連帯保証人を説明する前に「保証人」について説明します。
保証人とは、民法によれば、「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」と規定されています(民法446条)。
簡単にいえば、保証人とは、主たる債務者がお金を返済しない場合に、借りた人に代わってそのお金を返済することを約束した人のことですね。
そして、連帯保証人も、保証人と同様の人のことを言います。しかし、保証人以上に重い責任を課されているのが連帯保証人です。
下で具体的な「保証人」と「連帯保証人」の違いを紹介しています。
保証人と連帯保証人の違い
保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」と言った権利が認められています。
催告の抗弁権:「まずは借金をした張本人に請求してくれ」と主張する権利。
検索の抗弁権:「借金をした張本人の財産からしっかり返済をさせた後でなければ、支払わない」と主張する権利。
分別の利益:保証人が複数人いる場合に、人数に応じた平等の割合の金額分しか責任を負わなくてよいということ。
しかし、連帯保証人にはこれら権利が認められていません。
したがって、貸主が主債務者に請求せずにいきなり連帯保証人に請求をしてきても、連帯保証人は文句を言えないわけですし、仮に主債務者に多くの財産が残っているにも関わらず返済していない状況であっても、主債務者に代わって返済をしなければなりません。
また、保証する借金の金額についても、保証人のような人数頭割ではなく、連帯保証人の1人1人が、借金の全額について返済の義務を負うことになります。
つまり、お金を貸した側からすれば連帯保証人には、いつでも、いくらでも、借金額を上限として、返済を求めることができるのです。
連帯保証の地位は相続放棄によって回避することができる
ここまで読んで、連帯保証人の責任は大変重いものだということがお分かりになったかと思います。そして、被相続人が誰かの連帯保証人になっていれば、その立場を相続人は原則相続することになります。
おそらく、誰しもが相続人の連帯保証人の立場を相続したくないと考えるでしょう。
そこで、被相続人の連帯保証人の地位を相続しない方法として、相続放棄をすることが挙げられます。
例えば、亡くなった親が第三者の連帯保証人になっていたという場合があるでしょう。そういう場合にあっても、相続放棄をすることで子どもはその連帯保証の責任を回避できます。
ただし、相続放棄をしてしまうと、亡くなった親の家も預金も相続できなくなってしまうことから注意が必要です。
また、相続放棄をしたくても法律上放棄が認められていないという人がいます。その要件は「相続放棄をすべき人はどういう人?デメリットや判断のポイントを紹介」で確認してください。
また、相続放棄をする上での手続きについては「相続放棄の手続き|必要書類や申述の流れ・かかる費用について」をご覧ください。
連帯保証が原因で遺産相続トラブルに発展するケース

ここからは、連帯保証人になったことでトラブルになってしまったというケースを3つ紹介します。
ケース1:子どもが親の連帯保証人になっていた場合
亡くなった父親が商売をしていて、借金をする際に、子どもが連帯保証人になったというケースです。
ここで問題になるのは、連帯保証になった子どもが相続放棄をしたら、借金の返済義務を免れるのかということです。
結論から申しますと、子どもは借金の返済義務から免れることはできません。
なぜなら、連帯保証契約は、お金の貸主と子どもが直接結んでいるものだからです。主債務者である父親が死亡したとしても、その契約関係に変わりはありません。
このようなケースで連帯保証のトラブルに巻き込まれないためには、たとえ主債務者が親だからと言っても、安易に連帯保証人にならないことが必要となります。
ケース2:親が連帯保証になっていたことに気づいたのが遅かった場合
父親が亡くなってから1年後に、父親が第三者の連帯保証人になっていたことを知るというケースです。
この場合に、父親から相続した弁済義務を相続放棄できるかが問題になります。
まず、相続放棄には期限があり、その期限は相続開始を知ってから3カ月以内です。
つまり、相続開始を知ってから3カ月が過ぎた場合、相続放棄をすることはできません。今回のように被相続人が連帯保証になっていた事実を、後から知ったというケースにおいても同様に相続放棄はできません。
相続放棄ができないと、子どもは父親の連帯保証の義務を相続したことになります。
よくあるのは、主債務者が亡くなり、その債務者の相続人が相続放棄したから連帯保証人の元に返済の請求がきた。しかしその連帯保証人も亡くなっていたので、連帯保証人の相続人が返済義務を負うことになるというものです。
保証人になっていることは家族からは見えません。
ただし、被相続人には、プラスの遺産もマイナスの負債も無いと考えていたので相続放棄の手続を取っていなかったというケースでは、相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎてしまっていても相続放棄が認められる場合があります。
このようなケースの相続放棄は、なかなか難しいことから、弁護士に相談し、相続放棄手続きを依頼するのがよいと思います。
ケース3:親子で第三者の連帯保証人になっていた場合
例えば、父親がお世話になっていた人が借金をする際に、父親とその子どもが一緒に連帯保証人になっていたというケースです。
父親が亡くなった際、父親の連帯保証人の立場はどうなるのでしょうか。
原則、亡くなった父親の相続人がその保証債務を引き継ぎます。ただし、相続人が相続放棄をすればその借金返済義務から免れることができます。
一方で子どもの方はどうなるでしょうか。
この際、ケース1と同様に、貸主と子どもの連帯保証契約の関係は、父親が死亡したとしても変わりません。継続して連帯保証人の立場として返済義務を負うことになります。
亡くなった親が連帯保証人になっていたら弁護士に相談すべき

被相続人が連帯保証人になっていたとしても相続放棄をすることによって、その責任は回避できます。
しかし上記の「遺産相続トラブルに発展するケース」で紹介したように、相続放棄できないという状況に陥ることも存在し、それらは容易に解決するものではないでしょう。
さらに、相続放棄には期限がありますので、迅速な手続きが必要となります。
もし親が連帯保証人になっている場合には、弁護士に相談しましょう。
相続放棄を弁護士に依頼することには、
・相続関係に必要な書類集めの手間がかからなくなる
・熟慮期間である3ヶ月を過ぎることがなくなる
・債権者からの問い合わせや請求に自分で対応する必要がなくなる
このようなメリットがあります。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
親には、相続すべき遺産も負債もないと考えて、相続放棄の手続をしないでいたら、3カ月以上経過してから債権者から請求が来たというケースでは、相続開始を知ってから3ヶ月を経過しても相続放棄が受理される可能性があります。
このようなケースでは、弁護士に相談し依頼されたら相続放棄が認められるかもしれません。
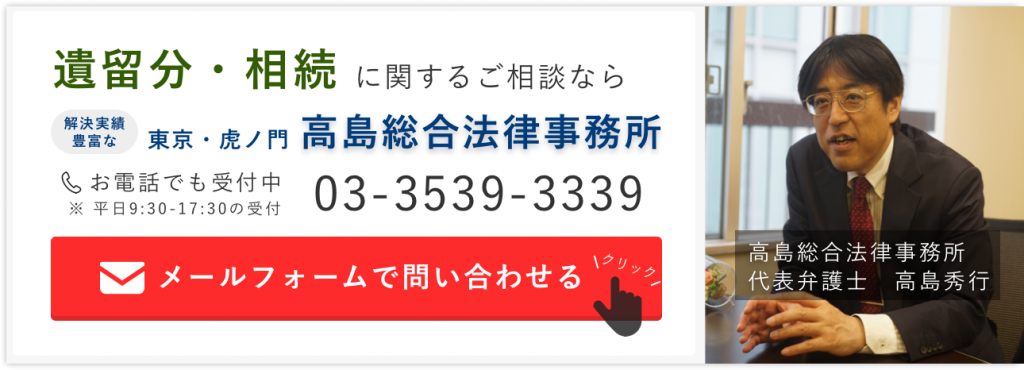
▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。
▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高島総合法律事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階
(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)
代表弁護士:高島秀行
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー