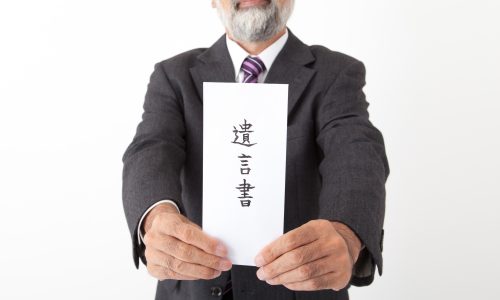「一度相続放棄をしてしまったけれども、その放棄をなかったことにしたい…」
この記事はこのように考えている方向けの記事です。
相続放棄を取り消すことができるのか、また相続放棄が無効になることはあるのかについて紹介しています。
目次
相続放棄の取り消し
相続放棄の申述書を提出してから受理されるまでであれば申立の撤回は認められますが、受理後の相続放棄の申述は取消ができるのでしょうか?
結論から申しますと、相続放棄の申述は、一旦家庭裁判所に受理されると熟慮期間であっても取消・撤回することができません。
相続の承認や放棄について取消・撤回を認めてしまうと、他の相続人や利害関係人に多大な影響を及ぼし、法的安定性に欠けるからです。
ただし、一部の場合では取消・撤回が認められるケースがあります。そのケースとは、民法総則や親族編が規定する取消の場合です。これを認めないと、相続人の保護に欠けることになってしまうため、取消・撤回が認められます。
相続放棄の取り消しが認められる場合

具体的に、相続放棄の取消ができる場合には以下の場合が挙げられます。また、これは相続の承認にも同様に取消が認められます。
民法総則の規定によって取り消しが認められるもの
・未成年者が親権者または後見人の同意を得ずにした承認・放棄
・成年被後見人が自らした承認・放棄
・被保佐人が保佐人の同意を得ずに、または保佐人の同意に代わる許可を得ないでした承認・放棄
・詐欺または強迫による承認・放棄
親族編の規定によって取り消しが認められるもの
・後見人が被後見人に代わってした承認・放棄
・後見人の同意を得たが、後見監督人がいるのにその同意を得ないで未成年被後見人がした承認・放棄
ただし、上記の取り消し事由は、実際上はほとんど当てはまらないケースが多いですから、一度した相続放棄や限定承認は、取り消せないと考えていただいた方がよいと思います。相続放棄や限定承認をする場合は、遺産を十分調査して慎重にされることをお勧めします。
相続放棄・限定承認の取消方法
相続放棄の取消には、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。申述書を提出することによって家庭裁判所が受理の審判をおこなわれ取消が成立します。
限定承認においても同様の流れによって取消がなされます。
相続放棄・限定承認の取消申述が受理されたら
相続放棄・限定承認の取消申述が受理されたら、相続放棄・限定承認ははじめからなかったことになります。
ただし、裁判所に相続放棄・限定承認の取り消しを受理されただけでは、取り消しの効果を主張したい相手方に対しても認められるとは限りません。相続放棄・限定承認取り消しの受理は、相続放棄・限定承認と同じように、形式的な審査しかされず、受理されたとしても実体法的に効果が生じるとは限らないからです。
あなたが相続放棄・限定承認の取り消しの効果を主張したい相手方が、取り消しの理由がないと争ってきた場合は、取り消しの理由があることを証明する必要があります。
取り消しはできるが…相続放棄が無効になることはあるのか
民法では、相続放棄の取消について定めているのみですが、無効の主張も可能とされています。相続放棄が錯誤によっておこなわれたケースでは無効が認められる可能性があります。
相続放棄の無効の主張については、取消のように家庭裁判所に申述をおこなうのではなく、裁判上もしくは裁判外において法律関係の前提問題として主張することになります。
相続放棄の際に錯誤があったために無効を認めた裁判例
・被相続人の母親が被相続人の兄弟に相続させることを目的に相続放棄したところ、すでに亡くなっていたと思われていた被相続人の祖母が生存していた
・税理士から相続放棄をしなければ多額の債務の支払い義務が生じると言われ相続放棄したが、それが虚偽の説明で、債権の方が多かった
・被相続人から多額の債務(借金)があると告げられていたため相続放棄をしたが、反対に多額の債権が存在していた
相続放棄の取消・無効を希望するのであれば

相続放棄を一度申し立て受理されたものの、取り消したい・無効にしたいと考えるあなたは何かしらの事情を抱えていることでしょう。
もし相続放棄の取り消し・無効をお考えであれば、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
前で説明したとおり、一度した相続放棄・限定承認の取り消しが認められるケースは限られていますし、実際上は、詐欺や強迫の取り消しについてもほとんど認められません。
詐欺や強迫による取り消しもそうですが、錯誤による無効主張においては、ただ申立をすれば良いのではなく、事実関係を元に法的に詐欺・強迫・錯誤に該当するかを主張しなければなりません。法律の専門家でない方が一人でおこなうと苦労をすることになるでしょう。
弁護士は相続に関するプロフェッショナルです。相談・依頼をすることによってきっとあなたの力になってくれることでしょう。
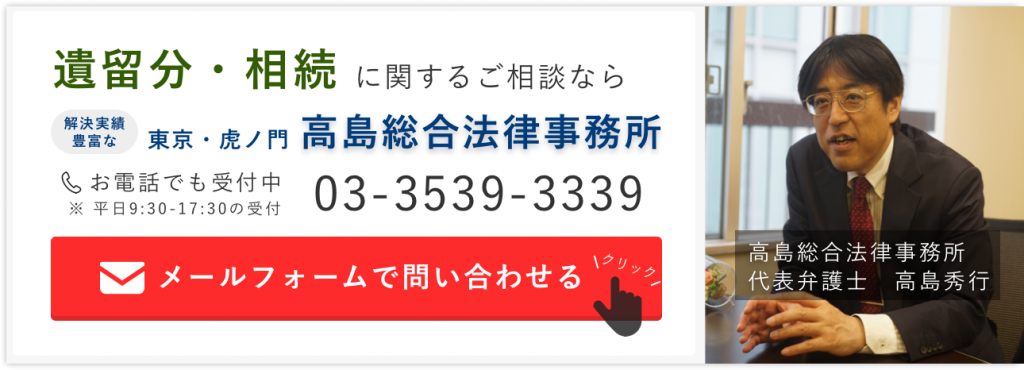
▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。
▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高島総合法律事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階
(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)
代表弁護士:高島秀行
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー