法定相続人にも関わらず、「相続権が無い」というケースがあります。「相続欠格」や「相続人の廃除」による場合です。
今回の記事では、「相続欠格」と「相続人の廃除」両方について具体的な事例とともに紹介します。
目次
「相続欠格」とは
相続権が認められている法定相続人となるべき人が特定の不正行為を行った場合に相続人となることができないことを「相続欠格」と言います。
いずれかに当てはまれば相続欠格、「相続欠格事由」は5つ
相続欠格事由とされる不正行為は以下の5つです。
① 故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にあるものを死亡するに至らせまたは至らせようとしたために刑に処せられた者。
② 被相続人の殺害されたことを知ってこれを告発せず、または告訴しなかった者。
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
①②は、遺産を巡っての殺人に関するものです。ドラマや小説にはありますが、実際にはあまり考えられません。
③④は、詐欺強迫により遺言を書かせたり、逆に遺言を書かせなかったりしたケースです。特定の詐欺や強迫によって書いたと遺言者が生前に弁護士等に相談して明らかにしておかないと、死後に証明することは難しいです。
⑤の遺言書の偽造や変造をしたり、破棄したり隠したりした人は相続人資格を失います。偽造された遺言書が出てきたとしても、なかなか誰が偽造したかまでは証明するのは難しいと思います。また、遺言書が破棄されたり、隠されてしまうと遺言書があったことや誰がその遺言書を破棄したり隠したりしたかを証明できないので、なかなか問題にはなりにくいです。
相続欠格となる具体例
「Aという土地建物は、Xが住んでいるので、Xに相続させる。Bというマンションは、Yに相続させる。」という遺言を残して、お父さんが亡くなりました。
その子であるXは、遺産を独り占めしようとして、遺言を隠して、BをX名義にしてから売却しその代金を分けようと提案しましたが、「しばらく貸しておいて欲しい。」と言って、代金を使い込んでしまいました。
その後Yが亡くなり、次いでXも亡くなりました。
Yの相続人QがXの相続人であるPに対し、ABについて遺産分割協議をしようとしたところ、Pは、AについてはXに相続させるという遺言書があるからXの相続人であるPのもので、Bについては、XとYが遺産分割協議をしてX名義にしたのだからいまさら遺産分割協議をする必要はないと主張しました。
ちょっと、複雑ですが、この場合、Xは遺言書を隠匿したので、相続欠格事由があることとなり、相続人とはなれません。
そこで、AをXに相続させるという遺言は無効となり、AについてはXの相続人であるPが代襲相続人としてY(Yが亡くなっているのでその子のQ)と遺産分割協議をすることとなります。
そうなると、Aについては、PとQが2分の1ずつ相続することとなります。Bについては、遺言によりもともとYが取得することとなっていたのですから全てYが相続することとなり、Yの相続人であるQはXの相続人であるPから代金を全額返還してもらえることとなります。
このケースは実際に、私が過去に依頼を受けた事件を脚色したものですが、隠した遺言が後から出てきて、遺言書の隠匿が発覚して相続人の欠格事由と認められた珍しいケースです。

「相続人の廃除」とは
相続欠格事由ほど重大なものではないけれども、推定相続人が一定の非行行為をした場合には、被相続人の意思に基づき家庭裁判所が相続人の相続権を失わせることができます。
これを「相続人の廃除」と言います。
いずれかに当てはまれば廃除できる、「相続廃除事由」は3つ
相続人の廃除をできる場合は3つの場合です。
①推定相続人が被相続人に対し虐待をしたとき
②推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき
③推定相続人にその他著しい非行があったとき
相続人の廃除をする方法
相続人の廃除をするには、2つ方法があります。
① 生前の廃除請求
生前に被相続人が、推定相続人が自分に対し虐待を行ったことを理由に家庭裁判所に相続人の廃除を請求する。
② 遺言による廃除
被相続人が、遺言書に推定相続人が自分に対し虐待を行ったことを理由に相続人の廃除をすることを記載します。被相続人が亡くなった後に、遺言執行者が家庭裁判所に相続人の廃除の請求をします。
いずれも、被相続人が生前に、家庭裁判所に廃除の請求をしたり、遺言書に記載したりしなければなりません。被相続人が亡くなった後では、相続人の廃除はできないので注意が必要です。
相続人廃除の具体例
お母さんが同居の長男や長男の妻から、暴力を受けていました。長女はこれを知り、すぐにお母さんを引き取りました。暴力を受けた証拠のお母さんの写真を撮って、診断書も取っておきました。そして、遺言書を作成し、遺産は全て長女に相続させるとして、長男については相続人から廃除すると記載しました。
これで、お母さんの死後、遺言執行者が相続人の廃除を家庭裁判所に請求すれば長男は、相続権が無くなりますので、遺留分を行使できません。
ただ、相続人の廃除は、相続欠格事由と同じく、代襲相続原因なので、長男の子供がいれば、代襲相続人として遺留分を行使できることとなります。
これも、私が実際に依頼を受けた相続人の廃除の事件を脚色したケースです。
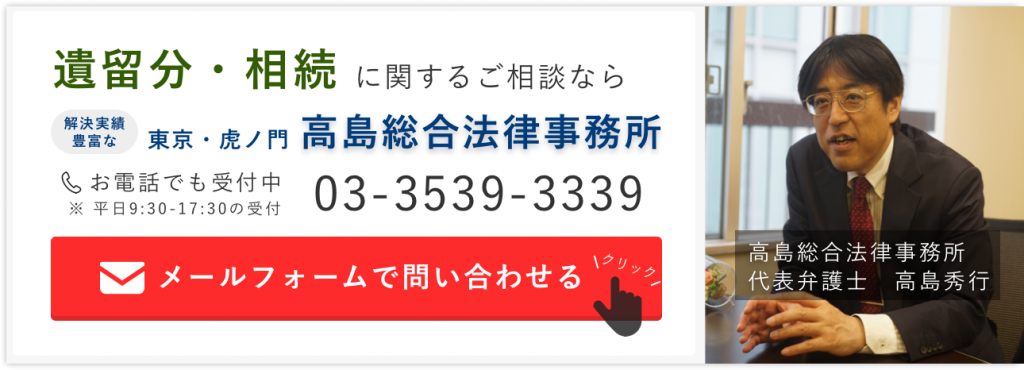
▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。
▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高島総合法律事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階
(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)
代表弁護士:高島秀行
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー














