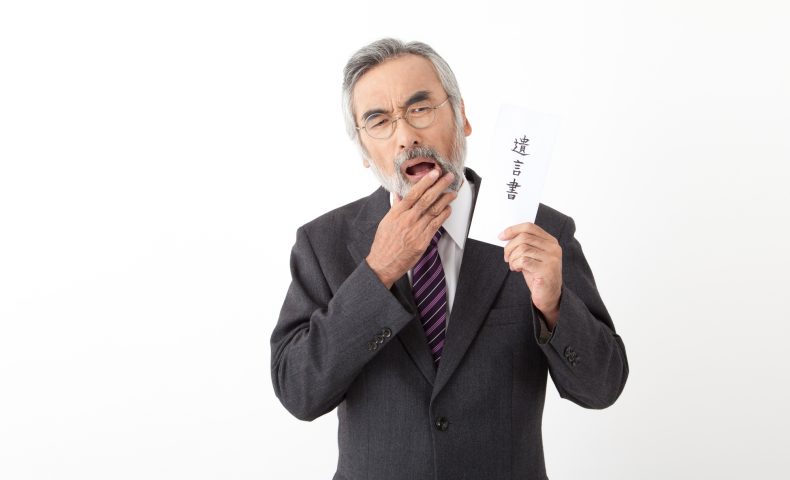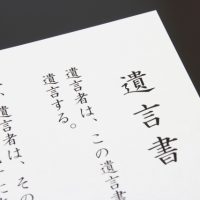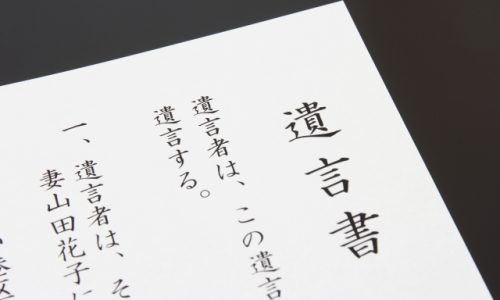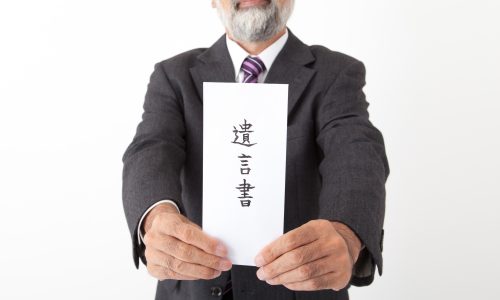目次
遺言執行者(遺言執行人)とは
遺言執行者とは、遺言に記載された内容を実現するために取らなければならない手続きをおこなう人のことです。
法律では遺言執行者の権限を広く認めており、遺言の内容を実現するために必要な手続き、すべてにおいての行為をおこなうことができます。
遺言執行者(遺言執行人)の権利・権限
遺言執行者に与えられている権利・権限について紹介します。
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利
| 【民法1012条】(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、相続財産の管理そのほか遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 |
相続財産の管理と遺言執行に必要な行為において、遺言執行者自らおこなう権利を持っているということです。つまり、これらの行為をおこなうのに委任状などは必要ありません。
また、遺言執行者にこのような権利が与えられているので、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません。
費用償還請求権
遺言執行者が、遺言の執行のために必要とされる費用を支出したり、債務を負担したりした場合には、相続人に対してその費用の償還もしくは弁済を求めることができます。
また、遺言執行者が過失なく受けた損害についても、遺言執行者は相続人に対してその支払いを求めることができます。
報酬請求権
遺言者(亡くなった方)が遺言によって報酬を定めれば、それにしたがって報酬を請求することができます。
もし遺言の中に報酬に関する定めがされていなくても、相続財産の状況やそのほか事情を考慮して家庭裁判所が報酬を定め、請求できます。
通常、これらの請求は直接相続人に対しておこなうのではなく、相続財産の中から支出されます。
遺言執行者(遺言執行人)がするべきこと・義務
遺言執行者は遺産について上記のような権限を与えられています。そして、同時に相続人に対していくつかの義務を負っています。どのような義務があるのか確認してみましょう。
善管注意義務
遺言執行者は、善良な管理者として注意義務を持って、遺言執行を行わなければなりません。自己の財産に対して払わなければならない注意以上の注意義務が求められます。
直ちに任務をおこなう義務
遺言執行者は、選任されたのち直ちにその旨を相続人に伝え、任務を開始しなければなりません。正当な理由がない限り、遺言の執行を先延ばしすることは認めらません。
財産目録作成の義務
遺言執行者は財産目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。財産目録とは、亡くなった方の相続財産のすべてをまとめ目録としたもので、預貯金・不動産・株式・車・貴金属など、相続財産となるものを列挙します。
報告義務
遺言執行者は、相続人から遺産処分の進捗状況について聞かれた際には、いつでも報告しなければなりません。くわえて、すべての作業を終えた際にも相続人に対して遅滞なく報告をする義務を負います。
受取物の引渡し義務
遺言執行者は、遺言の執行のために受け取った財産を相続人に引き渡さなければなりません。
遺言執行者(遺言執行人)になる資格のある人
遺言執行者には基本誰でもなることができます。
ただし、以下のいずれかに該当する人のみ遺言執行者にはなれません。
・未成年者
・破産者
破産者とは、破産宣告を受けた人のことを言います。
遺言執行者(遺言執行人)の選任・指定の方法
遺言執行者の指定は、遺言書への記載によっておこなわれます。
そのため、遺言書の内容を確認した際に、遺言書に遺言執行者の指定があれば、速やかにその指定されている方へ連絡しましょう。実際に遺言執行者としての職務を行えるのかを確認してください。
また、上記のように遺言者が直接、遺言執行者を指定するのが一般的ですが、そのほかに遺言執行者の委託を特定の第三者に委託することも可能です。
遺言執行者を複数人選任することもできる
遺言執行者は、複数人指定することも可能です。
その際に、遺言執行者の順位を決めることもできます。第一順位の遺言執行者が職務をおこなうことができない場合に、第二順位の遺言執行者が職務をおこなうということになります。
遺言執行者(遺言執行人)の指定がない・第三者への委託がない場合
遺言執行者の選任は任意です。そのため、遺言書の中で遺言執行者が指定されていないということは珍しくありません。
そしてもちろん、遺言執行者が指定されていないからという理由で、遺言の内容が無効になることはありません。
しかし、相続に関する手続きの中には、遺言執行者なしでは円滑に進まないというものもあります。このような場合には、遺言執行者を後から指定します。
その指定の方法は、相続人・利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選定するというものです。利害関係人なので、相続人でなくても、受遺者や相続債権者からでも申立てが可能です。
遺言執行者の選任の申立先
選任の申立先となる家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺言執行者の選任の申立に必要な費用
・執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手にかかる費用(申立先となる家庭裁判所へご確認ください)
遺言執行者の選任の申立に必要な書類
・申立書
・標準的な申立添付書類
・遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
・遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
・利害関係を証する資料
遺言執行者(遺言執行人)を断ることはできるのか?
遺言執行者として指定されていても必ずその任務を努めなければならない訳ではありません。たとえ、遺言書にて遺言執行者として選任されたとしても、そこには何ら拘束力はありません。
遺言執行者個人の意思で自由に断ることができます。
「仕事が忙しい」や「相続手続きに関わりたくない」といった理由で構いません。
その際、断りの意思表示は、相続人におこなうのが基本です。口頭でも文面でもどちらでも良いとされています。承諾の意思表示も同様です。
一度承諾した遺言執行者(遺言執行人)を辞任することはできるのか?
一度遺言執行者に就いた場合、その後に辞任することは原則できません。
正当な理由があった場合にのみ辞任が認められます。正当な理由とは、老齢・病気・長期の不在・職務の多忙などです。
これらを理由として、遺言執行者本人が家庭裁判所に「遺言執行者辞任許可審判申立」をおこない、家庭裁判所からの許可を得て辞任することとなります。
また一方で、相続人などが遺言執行者の解任を求めることも可能です。
遺言執行者を解任するには、家庭裁判所に対して遺言執行者の解任申立をする必要があります。申立により審判がおこなわれ、正当な理由があると判断された場合に解任が認められます。
遺言執行者(遺言執行人)を選任するメリット
ここまで遺言執行者の権利義務や遺言執行者の指定・選任の方法を紹介してきました。ここからは、遺言執行者を選任するメリットについて説明します。
選任しないとできない手続きが可能に
遺言執行者を選任しない限り、実現できない手続きがあります。例えば、相続人の廃除や廃除の取り消し、子どもの認知などがそれにあたります。
このような手続きを実現できるのが、遺言執行者を選任するメリットです。
相続人間のトラブルを未然に防ぐことが可能に
遺言執行者がいなければできないというものではありませんが、遺言執行者がおこなうことが理想とされる手続きもあります。その最たるものが、遺贈の履行となります。
遺贈は遺言執行者がいなくても、相続人に対し請求することができます。しかし、相続人は、遺贈を履行することは自分の利益にならないことから、協力をしない場合が多いです。
また、相続人が複数いたり、行方不明者がいたりすると遺贈の履行はなかなか円滑に進みません。
遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が遺贈の履行をすることができます。これにより、相続人が反対したり、協力しなかったりしても、遺贈の履行がスムーズにできることとなります。
その他に、土地を分筆したり、その他株式を売却したり、預金を解約したりして分けたりすることを遺言執行者に依頼することで、円滑に遺言の内容を実現することができます。
このように遺言内容を円滑に実現することが遺言執行者を選任しておくメリットとなります。相続人以外の第三者に対する遺贈がある場合は、遺言執行者を選任することをお勧めします。
遺言執行者(遺言執行人)に遺留分を請求できるか
遺言執行者が付いている場合、遺留分は遺言執行者に請求すれば、遺言執行者が遺留分を支払ってくれるのでしょうか。
遺言執行者は遺言に関しすべての権限を持つことから、そのように思われる方もいるかもしれません。
しかし、遺言執行者が遺留分減殺請求の相手方となるかという点については争いがあります。今のところ、過去の判例から、以下のように考えらえています。
遺言による執行が完了した場合には、遺言執行者は遺留分減殺請求の相手方にはなりません。受遺者又は相続させる遺言による遺産の相続人が遺留分減殺請求の相手方となります。
また、特定遺贈の場合は、遺言執行者は、遺留分減殺請求の相手方とはなりません。特定遺贈についても受遺者又は相続させる遺言による遺産の相続人が遺留分減殺請求の相手方となります。
遺言の執行が完了する前で、遺言で包括遺贈がなされている場合は、遺言執行者が遺留分減殺請求の相手方となるされています。
相続人が遺言執行者(遺言執行人)になった場合の報酬
遺言執行者の報酬金額がいくらになるかについてです。
遺言書に記載があれば、その記載の内容通りの報酬になります。もし記載がなければ、遺言執行者が家庭裁判所に申立をして、報酬金額を決めてもらいます。
相続人以外(専門家)が遺言執行者(遺言執行人)になった場合の報酬
最近では、遺言執行者を法律の専門家に依頼するケースが多くなっています。相続人の間で利益が相反する場合でも、第三者の立場から専門的な視点で判断されることになるからです。
専門家とは、具体的に、信託銀行・司法書士・弁護士が挙げられます。
依頼した際の報酬がそれぞれ異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
銀行・信託銀行に遺言執行者を依頼した場合
銀行。信託銀行に依頼した場合、最低報酬額が100~150万円で、相続財産の1~3%が報酬となります。
銀行によって、細かい報酬は変わってきますので、あらかじめ確認してみてください。
司法書士に遺言執行者を依頼した場合
司法書士に依頼した場合、遺産総額の約1%が相場といわれています。一般的に30万円程度になるでしょうか。
もっとも報酬の金額を安くするには司法書士に依頼するのが良いかと思います。
弁護士に遺言執行者を依頼した場合
弁護士に依頼した場合、法律事務所によってかなりばらつきがありますが、目安を知ることはできます。弁護士費用の目安となる、日弁連の規定によると、以下のようになっていますので参考にしてください。
このように、それぞれ金額に差があることがお分かりになるでしょう。
ここで注意していただきたいことは、費用が安いからという理由で、どの専門家・どの人に依頼するのか決めるべきでないということです。
遺言の内容を実現していく中で、トラブルになることがよくあります。しかし、遺言や相続についてのトラブルを交渉や裁判で解決する経験や知識を持っているのは、弁護士です。
遺言執行者には、資格は不要ですが、専門家に依頼するということであれば、弁護士をお勧めします。まずは相談してみてはいかがでしょうか。
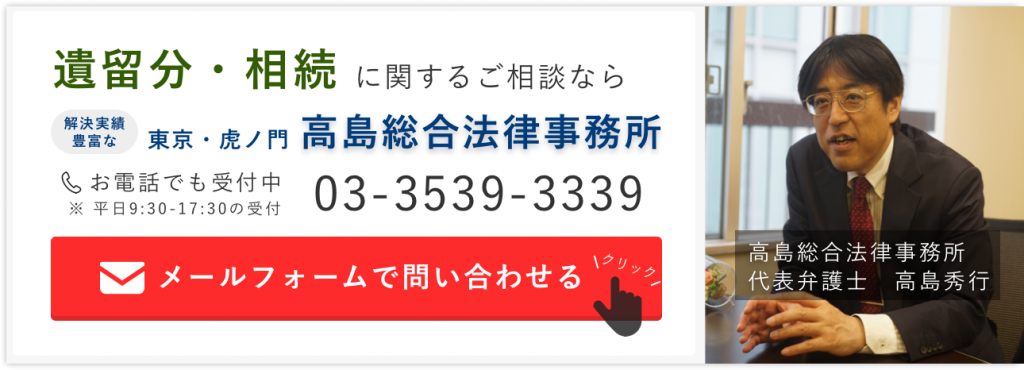
▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。
▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高島総合法律事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階
(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)
代表弁護士:高島秀行
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー