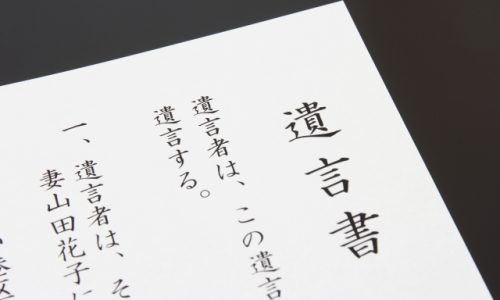目次
遺留分の放棄とは
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。この遺留分を放棄することを遺留分の放棄と言います。
遺留分について詳しく知りたい方は「遺産相続でトラブルが起きやすい「遺留分(いりゅうぶん)」とは?」をお読みください。
相続放棄は、相続開始後でないとできませんが、遺留分の放棄は、相続開始前でもできる点に特徴があります。
遺留分放棄が行われる具体例
長男が両親の面倒を見る代わりに、両親は全財産を長男に相続させるという遺言を書いて、妹が一定の生前贈与を受けて遺留分を放棄するなどがあります。
遺留分放棄を行う目的
遺留分放棄の目的は、相続開始後に、遺留分を巡って、相続人間で紛争が生じるのを防ぐことにあります。
相続開始前に遺留分の放棄をしてしまえば相続開始後に遺留分を巡って紛争が生じることはなくなるからです。
相続開始前と相続開始後で異なる遺留分放棄の手続
遺留分の放棄は、その遺留分放棄が相続開始前か相続開始後かによって、取らなければならない手続きが異なります。
(1) 相続開始前の遺留分の放棄
相続開始前の遺留分放棄は、遺留分権利者が家庭裁判所に許可の申立をして、許可を得なければなりません。
先ほどの例で言えば、妹が遺留分を放棄するので許可をしてくださいと家庭裁判所に申立をすることになります。
許可は、以下の3つのことが考慮されると言われています。
① 遺留分を放棄することが放棄をする人の自分の意思によるのか(強制されていないか)。
② 遺留分の放棄に合理的な理由があるか。
③ 放棄に見合う代償を得ているか。
(2) 相続開始後の遺留分の放棄
相続開始後の遺留分の放棄は、裁判所の許可は必要ありませんし、書面による必要もありません。
遺留分を放棄する人の自分の意思によれば、合理的な理由がなくても、放棄に見合う代償を得ていなくても、遺留分の放棄は有効となります。
「遺留分放棄」と「相続放棄」の違い
相続放棄は、相続開始前にはできません。
これに対して、遺留分の放棄は、相続開始前にも裁判所の許可を得ることによってできます。
これが相続放棄との大きな違いです。
また、相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所に申述する必要があります。
一方で、遺留分の放棄は、相続開始後は、家庭裁判所に申立をしたりする必要はありません。
「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。
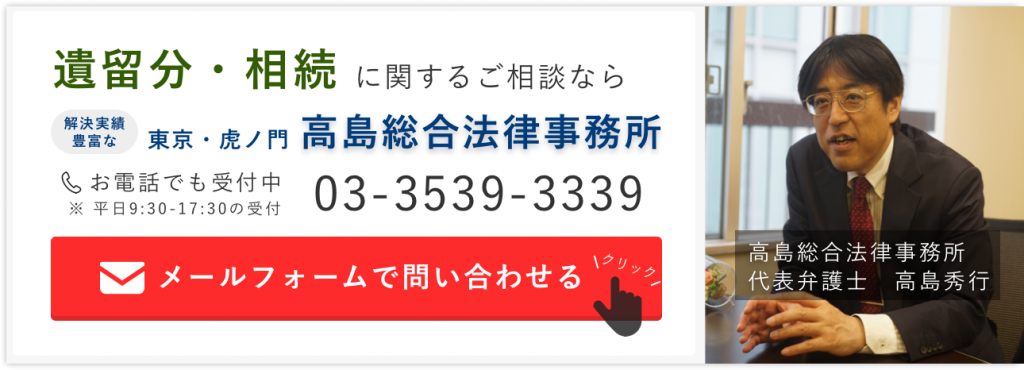
▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。
▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高島総合法律事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階
(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)
代表弁護士:高島秀行
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー